分厚い円盤型をした、生地の中にあんこなりカスタードを入れて鉄板の型で焼いた「あの菓子」に地域ごとで様々な呼び方があるように、味噌も地域ごとで食されているものが違う。カップ麺のうどん・そばの出汁のように関ヶ原で二つに分けるなんて到底できそうもない。
日本各地の味噌を使った、バリエーション豊かな味噌ラーメンを提供するチェーン店があちこちに展開しているから、今では各地の味噌の味を気軽に楽しむことができてよい時代になった。一度買ってしまうと、口に合わなくてもその味噌を使わないといけないのはちょっとしんどい。僕は関西に住んでおきながら、白味噌にどうも馴染めず、ずっと冷凍庫に眠らせてしまっている。
地域ごとの味噌の傾向、というのはもちろんあるが、家庭ごとにも味噌の違いというのがあるだろう。地域が離れたもの同士で共に暮らそうものなら、味噌の違いというのは問題として立ち上がってくるのではないだろうか。とはいえ、今では信州味噌が全国シェアトップだから、思ったよりも問題は起きないかもしれない。しかし、それは家庭の味の画一化が進んでいる証でもある。
「手前味噌」という言葉がある通り、昔は各家庭でも味噌を作っていて、そして文字通り味噌は家庭の味そのものだった。父の実家は正月の雑煮でも白味噌を使わずに自家製の味噌を使うくらいにはそれを重んじていた(単に面倒だったからかもしれない)から、僕は白味噌よりも、しっかり熟成期間をとっていて、色も風味も深い味噌を好むようになったのではないかと思う。
とはいえ、その味噌はほとんど我が家にはもたらされておらず、子供時代はだいたいマルコメの出汁入り味噌で育ったように思う。それでも、強烈に郷愁を掻き立てられるのは、やはり父の実家で食べた味噌汁なのだ。そんな自家製味噌だが、祖母の死後しばらくありつけずにいたところ、叔母が今でも作っているというので、少し分けてもらっていた。しかし、一汁一菜を習慣としたことで、分けてもらうだけでは足りなくなってしまい、とうとう味噌を自分で作ることにしたのである。
数えきれないほど味噌を作ってきて、周囲からも「味噌名人」の呼び声高い叔母の手引きによって、去年(2025)に引き続き、今年(2026)も味噌を仕込んできた。仕上がりはだいたい半年後。お盆の頃には、しっかりと茶色くなった味噌ができあがる。
その様子を、去年と今年の写真を織り交ぜてではあるが、工程順に写真でお送りする。

まず、前日から浸水しておいた黒豆を圧力鍋で炊く。このときの柔らかさの基準は、利き手でないほうの親指と薬指でも潰せるほどと叔母はいう。要するに、力が入らない指でも潰せるぐらいに柔らかく煮るのだ。そして、それをミンチ製造器(手動)でどんどんミンチ状にしていく。

ミンチになったら、手で持てる熱さになるまで冷ましておく。


塩と米麹を混ぜておき、豆を受け入れる態勢を整えておく。


叔母曰く、「米麹を下に擦り付けるように」ミンチにした豆と米麹を混ぜ合わせる。これがなかなか重労働だが、結構面白い。


しっかり空気を抜くようにして容器に詰め込んだら、空気が入らないようにフタをする。味噌は嫌気性発酵なので、表面が空気に触れないように、なにか密閉できるフタをしないといけないのだが、そこで叔母が取り出したのが酒粕である。これを練って味噌の赤ちゃんの表面が見えないようにピッタリとフタをしてしまう。あとは容器のフタをして、冷暗所で半年ほど放置する。
だいたい豆が冷め切っていない状態でここまで進むので、翌日朝には容器の中や容器のフタの裏にぴっちり水滴がついている。これは必ず確認して拭いておこう。なにせ、「正解は半年後」であるから、ここで失敗の素を放置してしまうと、取り返しのつかないことになる。豆の潰し具合も、米麹との混合も、「だいたいこんな感じでええやろ」と進んでいくが、容器内の水滴だけは慎重になったほうがいい。

半年経てば、このように酒粕が茶色に染まっていて、よい香りが漂っている。酒粕のフタを外すと中から味噌が登場する。

味噌づくりにおいて人間ができるのはお膳立てだけで、あとは発酵のはたらきに任せるしかない。工業的に作られる味噌でも、できるのは発酵の促進であって、発酵(ないし腐敗)そのものは人間の手によるはたらきではない。
自分で味噌を作ってみれば、みんなもう少し、人間の力の及ばない領域があることを理解できるかもしれないが。
今回の一汁一菜

2025/12/10分
ベーコン・ピーマン・キャベツの炒め味噌汁
ゆず大根
ベーコン・白菜の炒め物(父親作)
父と僕でベーコンが被ってしまった。示し合わせては料理をしていない弊害が出たが、まあ別にいい。ピーマンは畑で採れた、本当に今シーズン最後の最後のピーマンだった。
「なごり」のピーマンは少し苦いが、それもまた季節の味といえるだろう。
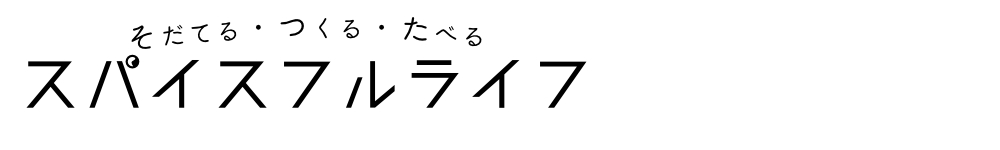


コメント