はじめに
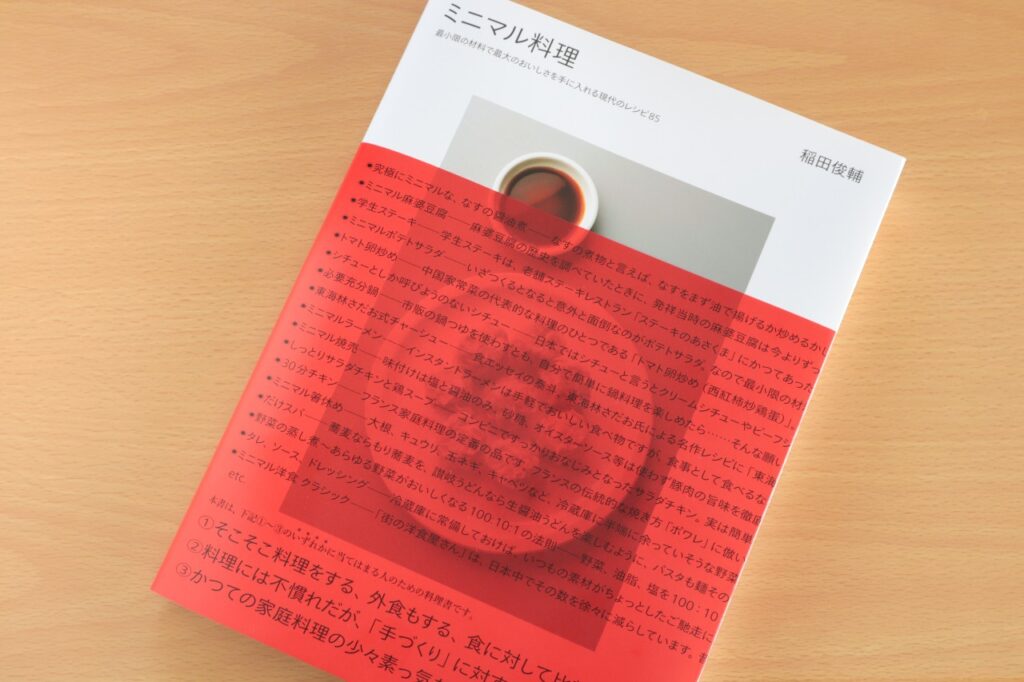
こんにちは。ハセガワタクミ(カルダモン26)です。
今回は、稲田俊輔さんの料理本「ミニマル料理 最小限の材料で最大のおいしさを手に入れる現代のレシピ85」の紹介です。
後に本の中から作ったレシピの一部も紹介しますが、今ではもうぐっさりと私の生活に入り込んだ一冊となっていて、何を作ろうか考えるとき、気がつけばこの本を開いているほど。
そこまでハマった一冊ではありますが、最初にこの本を見たとき、正直ぎょっとしました。
最近よく聞く「ミニマル」という言葉が意識の高さを感じさせるのです。それに、表紙のミニマルなシュウマイの佇まいと、文字がぎっしりの赤い帯。「自分が買っても大丈夫な本なのか……?」とちょっと心配になりました。
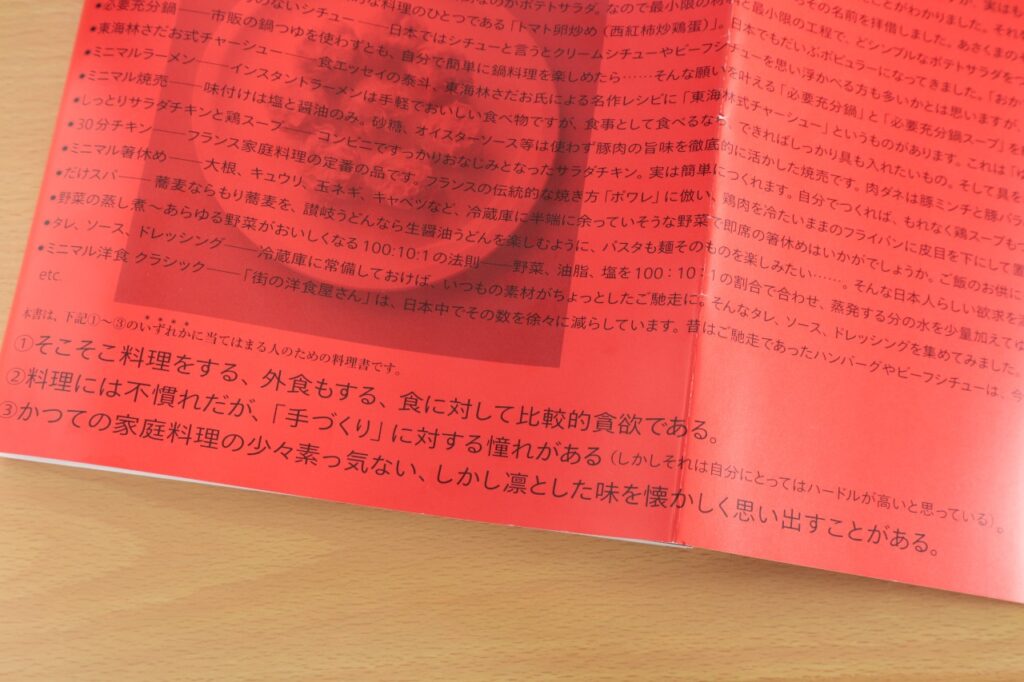
事実、この本は2023年のレシピ本大賞にて、「プロの選んだレシピ賞」を獲得。その道のプロが認めたというレシピが揃っているのだから、さぞかし難しいのかと思って本を開けば、それは杞憂に終わりました。
レシピはとにかく明快。「ミニマル料理」という題の通り、少ない食材の種類で済みます。経済的であるのはもちろん、あれこれ揃えなくてよいのだから、ある意味初心者に優しい本です。だからこそ、この本は「料理に不慣れだが『手づくり』に憧れのある人」も読者として想定されています。実際、複雑な工程を踏むことはほとんどありません。
「ミニマル料理」の想定する読者の条件(以下、「ミニマル料理」帯より引用)
①そこそこ料理をする、外食もする、食に対して比較的貪欲である。
②料理には不慣れだが、「手づくり」に対する憧れがある(しかしそれは自分にとってハードルが高いと思っている)。
③かつての家庭料理の少々素っ気ない、しかし凛とした味を懐かしく思い出すことがある。
それがどうして「プロが選んだレシピ」なのか。それは引き算の難しさをプロは誰よりも知っているから。より多くの人に「美味しい」と言わせたいなら、味は濃くなったり、甘くなったり足し算の方向に行きがち。でも、この本では一度引き算してみせて、再度その料理を再構成するのです。そこにあったのは、これまであなたが見落としていた美味しさです。
他の料理本と何が違うと感じたのか
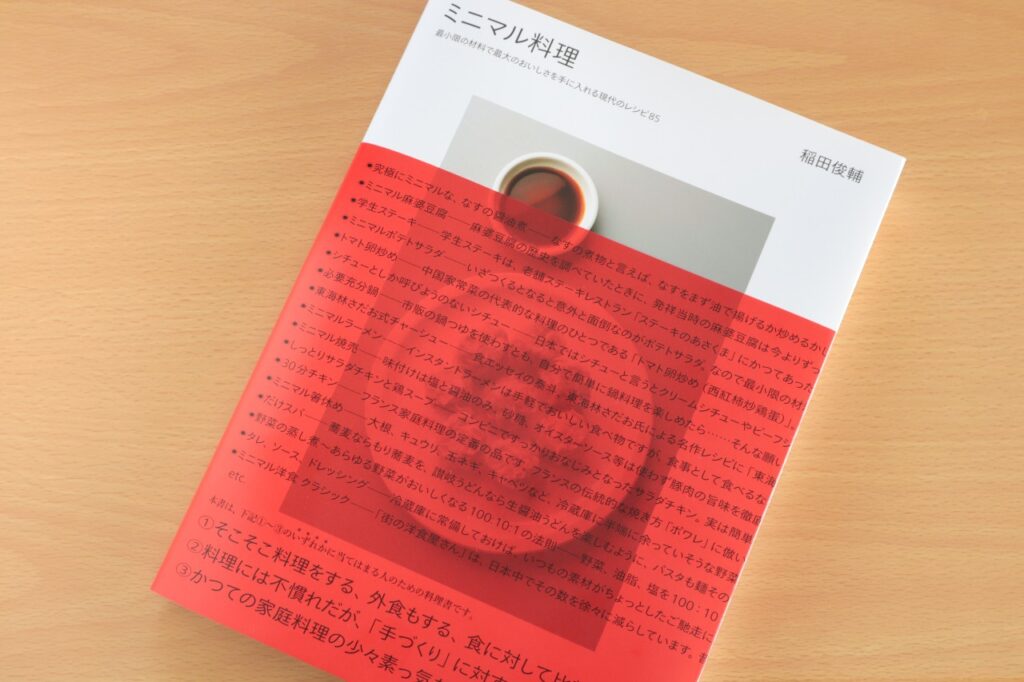
削る難しさと再構成する歓び
「家庭でもプロの味」を謳う「○○入れるだけ調味料」などの、ありとあらゆる調味料があふれ、複雑で、ときに過剰ともいえる味わいの料理が蔓延る今の世に反旗を翻すように現れたこの一冊は、「最小限の材料で最大のおいしさを手に入れる」ことを謳います。
一旦「その料理がその料理たる最小限の要素」までそぎ落としたあと、何が必要かを今一度吟味し、レシピを再構成する……そんなレシピがこの一冊には詰まっているわけですが、ここにゾクゾクと知識欲と実践欲が掻き立てられるものがあります。
単にレシピが書いてあって、これを作ればいいというのではなく、この本のレシピを作り、自分の「美味しい」の尺度がどこにあるか確かめる。そして、次に作るとき自分ならどうするかを考える。そうやってレシピと対決することに歓びを感じさせてくれる本です。
かつての家庭料理への郷愁
レシピは日々進歩するものです。そして「最高」「究極」「一番美味しい」……レシピの枕詞も日々その規模を広げ、やがてこの宇宙を包み込むほどの勢いです。そんなレシピたちは確かに美味しいのですが、「美味しいと思わされている」と私は感じることがありました。写真や動画を通し、目を、舌を、耳を、そして脳をハックするためのノウハウもすっかり成熟しているように思います。画面越しでも匂いがする技術が実用化に至り、鼻までハックされたら、もう完全に乗っ取り完了。
でも、それに抗いたくなる私がいたのです。自分が欲しい「美味しさ」はこういうのじゃない――
私が求めるのは、シンプルで飽きがこなくて、何度でも食べられる料理。私の10年の家庭料理経験から、家庭料理ならばそうであるのが好ましいと考えています。その考えを育ててくれたのは、長年読み続けてきた「おかずのクッキング」。
しかし、2022年の放送終了と共にテキスト本も廃刊。私の味方となってくれる本がなくなってしまった……!とショックを受けていた時に出会ったのはこの「ミニマル料理」でした。

この本で紹介されている黄色い「基本の昔カレー」を食べたとき、私はそれが食べられていたであろう時代に生まれておらず、味も知らないはずなのに何故か「懐かしくて美味しい」と感じたのです。今は亡き祖母の料理と通ずるものを感じたのかもしれません。祖母の立っていたキッチンに特別な調味料はありませんでしたが、いくらでも食べられるような美味しい料理をこしらえてくれたのです。とにかく煮物が美味しかった……
こんなふうに郷愁に浸ってしまうような味に私は強く感銘を受けました。
どうしてこんなにも懐かしさを感じるんだろうと思い、「ミニマル料理」の前書きをよく読んでみると、著者の稲田氏は古い料理本、特に古い家庭料理の本が好きで、そこに書かれたレシピの味わいは「案外素っ気ない」としつつも、現代では失われつつある「凛とした飽きない味」を見つけたといいます。そして、そのレシピへのリスペクトをふんだんに盛り込みつつ、現代までそのまま進化していたらどうなるか?というのを検証したのが「ミニマル料理」だというのです。
新しいモノ好きな人間の性質上、流れていった過去のものを顧みるということはほとんどありません。特にレシピは流行り廃りの激しいもの。だから、こんなふうに、かつて存在したレシピに目を向けて価値を再発見し、現代向けに再構成するというレシピ本はなかなかありません。
温故知新。新しいモノは本当によいものなのか?昔にあったモノの価値は?そう考えるあなたにはぜひ読んでほしい一冊です。
「料理に不慣れな人」でも計量すれば大丈夫

ここまで思いっきり料理に関心の高い人向けの内容だったので、「ミニマル料理」がターゲットとしている「料理に不慣れだが『手づくり』に憧れのある」人向けの内容を。
これはこの本だけでなく、稲田俊輔氏のレシピ本の特徴なのですが、本当に好きなだけ入れてもいいもの以外は「適量」の表記が排され、全ての材料・調味料が計量されています(多くはグラム単位)。
「いちいち計量するなんて」と思われるかもしれませんし、「料理に不慣れ」ならなおさらと思われるかもしれませんが、毎回ブレる味付けや、味付けの失敗で一喜一憂するぐらいなら、きっちり量って安定した味わいを作るほうがよいと私は考えています。
「料理に不慣れだけど、手作りに憧れがある人」に対してこの本を稲田氏が薦めているのは、計量することで、ブレのない味わいを作ることができるほか、まずは、稲田氏が考える正解を知り、そこから自分好みにアレンジしてほしいという考えがあるのではないのでしょうか(あくまで私の想像ですが)。
また、これは私の考えですが、そうして自分の中に味付けの軸を持つことで、ネット上の玉石混淆なレシピから、よいものを見つけ出す目が養われると思います。
*****
そんな「ミニマル料理」レシピの中から、早速いくつか作ってみたので感想を書きます。
実際に作ってみた
帳尻合わせワンタン

最初に作ったのは、表紙にもなっている「基本のミニマル焼売」からの展開であるワンタン。
なぜ焼売ではなくワンタンかといえば、すでに「dancyu」2022年1月号「新しい家中華」(外部リンク)内で紹介されていた稲田氏の焼売を作ったことがあるから。
ちょうど先日上げた「キャベツのシュウマイ」で使った焼売の皮が余っていたので、本を読み終えると早速作りました。
焼売を作ると余りがちな皮。
これを使いきるためのレシピとしての「帳尻合わせワンタン」でしたが、このために肉ダネを作ったのはご愛敬。
稲田氏の肉ダネは何回か作っていますが、やはり美味い。
あれこれ入れないからこその、力強い味わい(これが「凛とした味わい」か!)があります。
タレの酢は黒酢を使い、ブラックペッパーや花椒入りのラー油を適宜かけながら楽しみ尽くしました。
基本の昔カレー

もちろん、稲田氏といえばのカレーのレシピも掲載……なのですが、ちょっと様子が違います。
なんと、往年の「黄色いカレー」を作れるレシピが載っています。


どシンプルな具材から繰り出される昔カレーは、一口頬張ると野菜の甘みがわっと押し寄せ、そのあとカレー粉の香りが花開いていく味わいは、昔を知らないけど、こういうのでいいんだよと言いたくなります。
食べ終わるとすぐにまた食べたくなり、おかわりを身体から欲するような感覚が生まれる……これが家庭料理だよなと再確認した逸品です。
カレー好きなら、この原点の味、抑えておくべし。
だけスパ

これだけ?と思うほど少ない材料(材料欄は3つ!)ですが、これで必要十分だと思い知らされたパスタ。
これまたちょうどほうれん草があったのでほうれん草の「だけスパ」にしました。
少し塩分強めで茹でたパスタに、ちょっと焦がし気味のバター、そしてほうれん草の甘み……本当にこれだけで美味しいのです。
「だけスパ」の章は後半ということもあり、稲田氏の筆が乗っているのか、全体的にテンションがおかしい(褒め言葉)。
あらゆるものを削ったミニマルなパスタが続きますが、「概念明太子スパ」でとうとう明太子がいなくなったときには続きが読めなくなるぐらい笑ってしまいました。
東海林さだお式チャーシュー〈改〉

東海林さだお式チャーシュー〈改〉を使って今治名物の焼豚玉子飯(のようなもの)を作ってみました。
手がかかりそうなチャーシューですが、まさかの煮てから醤油に漬けるだけ。


シンプルな作り方でもしっかりチャーシューで、豚肉の旨みがダイレクトに来るのが美味い!
あまりの手軽さに、すっかりリピート料理の一つに。
自宅でチャーシュー麺も、ゴロゴロ焼豚チャーハンも自由自在です。
限界ラーメン

水と醤油とその他諸々で作る、「ラーメンと感じられる限界」を攻めたようなレシピ。
一口すすれば、「ええっ、ああ、ラーメンや……」と感嘆しました。
スープを沸かしているときは「まさかぁ~」と疑っていたのですが、ゴメンなさい。これはラーメンです。
書いている今気づきましたが、「帳尻合わせワンタン」を載せるとまた旨そうです。
ほかにも、排骨麺などの具材を載せるときのベースの麺として最適。おいしいけど、「旨すぎない」からこその魅力があり、まだまだ楽しみは尽きません。
ほかにも作ってみた

この写真のうち、ハンバーグにかかっている「ハッシュドビーフ風ソース」や付け合わせの「ミニマルポテトサラダ」、漬物の「生姜キャベツ」も「ミニマル料理」掲載のレシピ。
稲田氏といえばカレーのイメージが強いですが、この本にはあらゆる分野の料理が掲載されていて、痒い所に手が届きます。メイン料理からサブの付け合わせや箸休めまで、あらゆるシチュエーションで、まさに一生使えるような一冊になっているのではないでしょうか。
おわりに
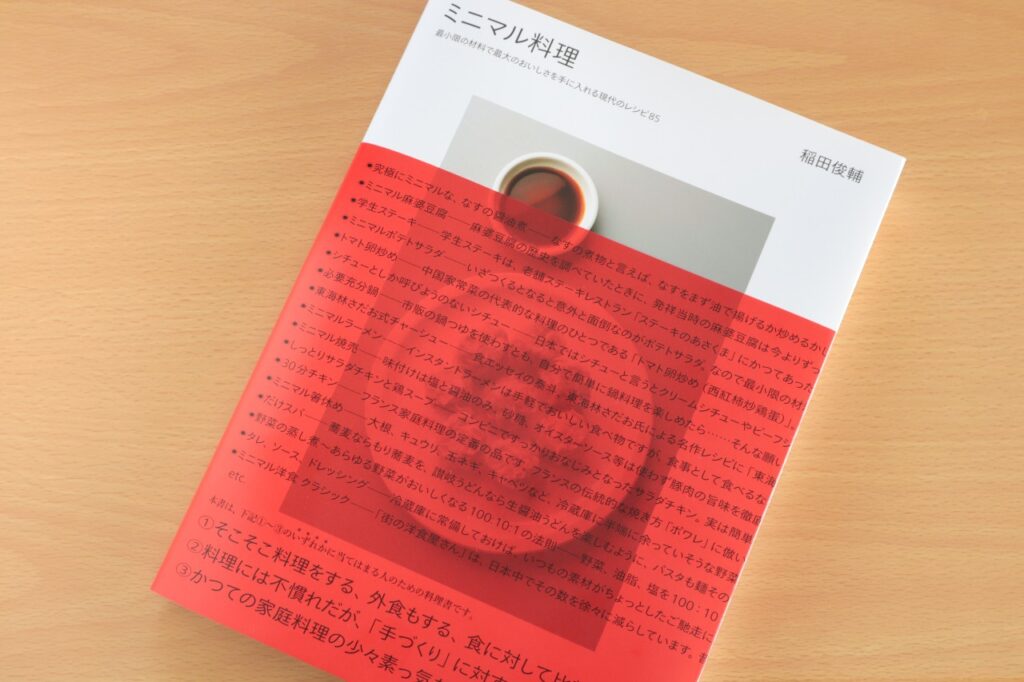
料理本を買っても、「こんなん作れへんわ」と結局作らずに本棚の奥で腐らせる……ということがしばしばあると思われますが、「ミニマル料理」のレシピにはそんな心配全くありません。
上で作ったレシピは、いずれも「ちょうど〇〇があるから」作りました。
「必要」とされているものが少ないがゆえ、気楽に試せるレシピばかりです。
そして、それらはかつて「家庭の味」として親しまれてきたもの(のアップデート版)。
「家庭の味」として毎日食べるのであれば、飽きのこない、シンプルな味わいがよいというのは実際に作って食べて、非常に納得感のあるものでした。
それを踏まえ、改めてこの本をおススメしたいのはこんな方々です。
・「あの味をもう一度」と思う方には超おススメ。 ・食への探求心が強い方にも超おススメ。 ・「これから手づくりの料理を作ってみたい」という方にもおススメ。 玉石混淆なレシピに惑わされたくないのであればなおさら。
そして、レシピを発表している身としては、「本当にこれは必要な調味料なのか」と自分のレシピを省みるきっかけとなった一冊でした。玉石の“石”にならないよう精進したいと思います。
ここまでご覧いただきありがとうございます。

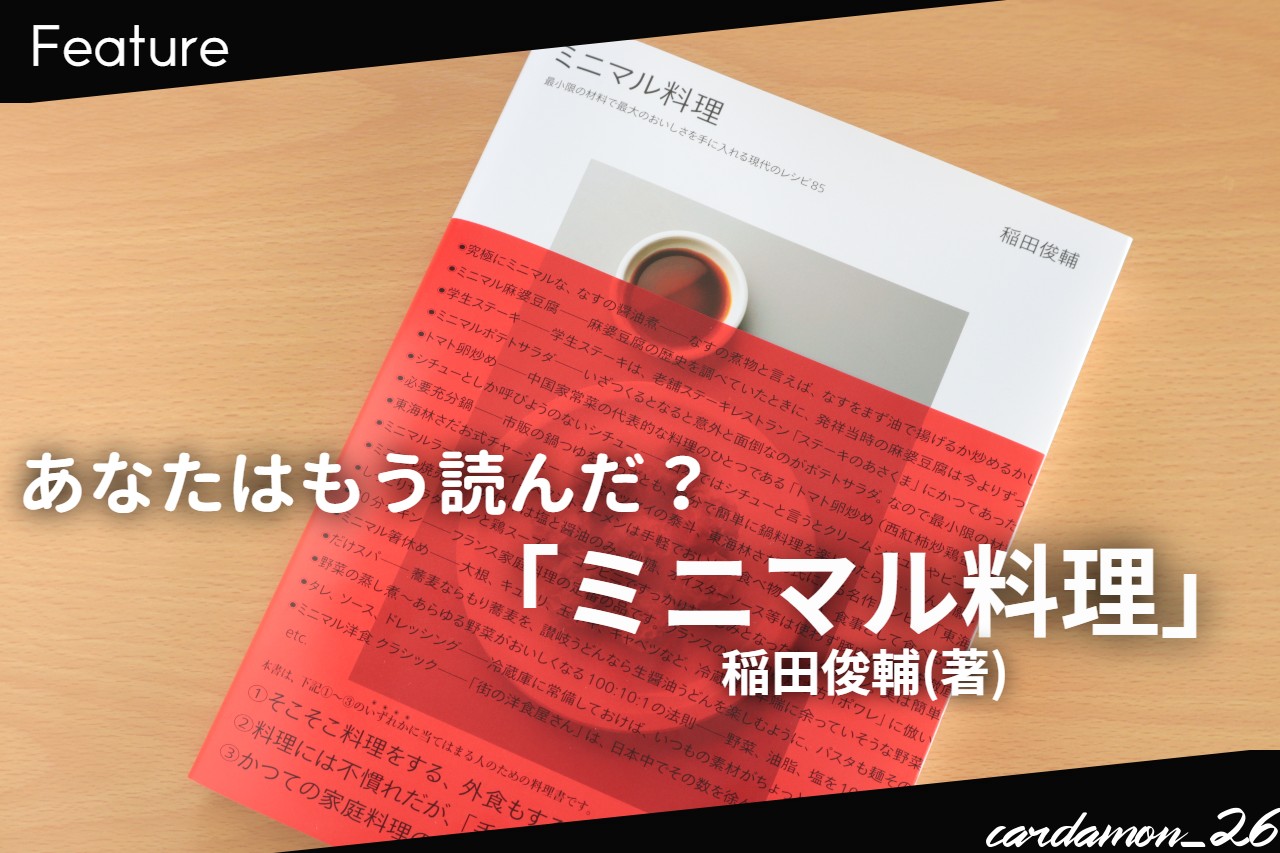




コメント